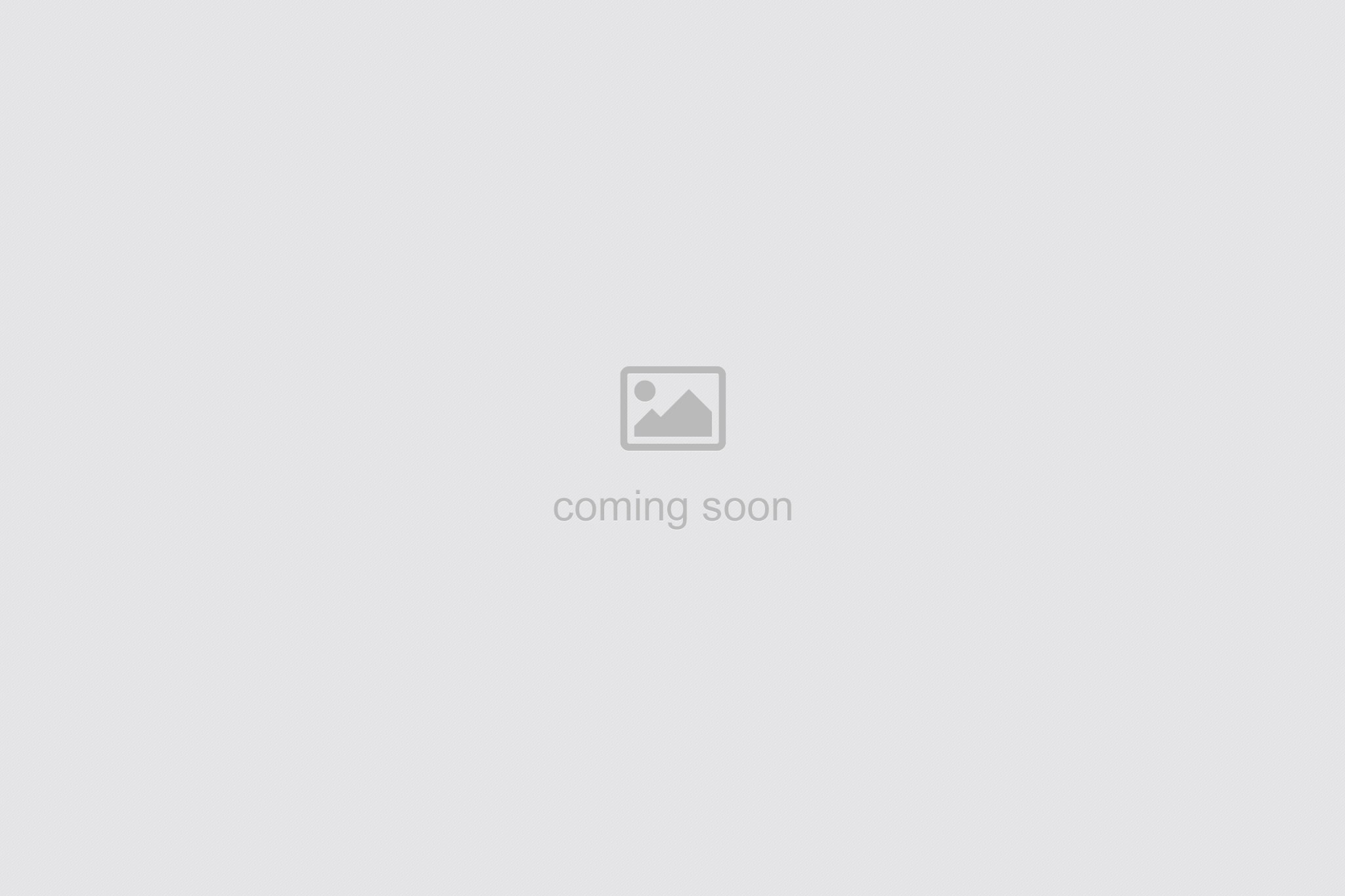ナスコニュースの続きはこちら
第22号巻頭ページの続き
2024-10-20
記憶の陰影(短編小説) written by Yoshi
満員電車に揺られながら、彼の頭は見つからない名刺入れのことから離れない。先日の商談で交換した名刺が入っている。会社に置き忘れたのだろうか。「ま、会社に着けば分かることだ。」と自分に言い聞かせるように呟いた。周りの乗客がその呟きに反応してチラッと彼に目をやった。ふいに粘りつくような視線を感じる。視線を移すと、その気配は消える。しかし、ぬぐい切れない不安感がまとわりついた。それにしても…あの商談の日から妙に気になることがあった。商談の相手のことだ。どっかで逢ったような気がする…。
デスクの引き出し、バッグや書類の間まで探したがみつからない。まずいな。常務案件なのに。常務の罵声が聞こえそうで、彼は頬の筋肉がひりつくのを感じた。最後に名刺入れを確認した日、いつだったのか、商談の日が四日前いや五日間だったか。その後、どうした。昨日はあったはずだが。どうもはっきりしないな。盗まれたのか? ふと、気づいた。ないのは名刺入れではない。記憶だ、記憶が盗まれたのか。なら、どこかに隠されているはずだ。とうに彼の自分の顔色は変っていた。周りの同僚たちはそんな彼を歯牙にもかけないふりはしているが、内心では薄笑いしていた。
「どうした? 君らしくないな。」と声がする。見ると同僚が彼の顔をのぞき込んでいる。彼にはそれが誰か思い出せない。「誰だ…、お前か?盗んだのは」と声にならない声で問うた。同僚は彼の虚ろな目に眉をひそめて、「先に帰るぞ」と部屋を出て行った。口元に皮肉な笑みが滲ませながら。
彼にはその男が同僚だと気がつかないほど混乱していた。オフィスを後にした同僚はあの頃を思い出していた。新製品が大ヒットした時のことだ。「あの頃は、絶えず品不足に悩まされた。ヤツはいつも倉庫に出入りして商品を独り占めしやがった。何度も、全体のことを考えろと、口論になったがヤツは意に介さなかった。勝手なヤツだ。」
続きはここから↓
彼は混乱しながらも考えた。「さっきの男は一体誰だ?… あいつか」。あいつとは、部長にこっぴどく叱責されて退社していった部下のことだ。商品が届かないと得意先から苦情が入った。あのヒット商品の件だ。あいつは、自分の割り当て分で得意先への配送手配を完了していた。しかし、その手配が、後でこっそり変更されていた。「要領の悪い奴だ。」 あいつは退社の日、蔑むような眼を彼に残して去って行った。あの目はあいつか…? 別の顔が浮かんできた。良く出来た新人だった。ある日、大口案件を掴んできた。相談に乗るそぶりを見せながら自分の成績にした。その新人の目は憎しみと哀れみを湛えていた。その後も次々に彼の前を去来した人の顔が浮かんでは消えていった。
彼は怯えた。高層階の窓の外に、街の灯が明滅している。遠い空で雷光が闇を切り裂いている。視界を巡らした時、彼はギョッとした。窓の外から何者かがこちらを凝視している。すぐに窓に写った自分の顔だと知ったが、髪が逆立ち、目が血走った鬼の形相だ。心臓が一瞬収縮した。全身の血管に痛みが走った。「あれが俺の正体だというのか。」と次の瞬間、鬼の形相は商談の男の顔に変化した。さらにその顔はゆっくりと「あいつ」の顔に変わっていった。蔑むような眼が張り裂けるばかりに見開き、咆哮し、彼を威嚇してきた。そして襲ってきた。恐ろしさのあまり彼は悲鳴のような声をあげた。その時、恐ろしい閃光が炸裂したかと思うとすさまじい雷鳴が轟いた。窓ガラスは破れんばかりに振動した。激しい恐怖に錯乱し事務所のなかを暴れまわった。名刺入れを失くし、記憶を失くし、遂には我をも失くしてしまった。電話機といわず、書類トレーといわず、デスクの上にあるはずのあらゆる物が床に散乱していた。
どれほどの時が経ったのか、疲れ果てて、朦朧と床に倒れ込んでいた。彼の前に、青白い霧が立ち込めた。その霧の中に、仙人のような老人が現れた。彼はその顔を見た瞬間、遠い日の祖父の記憶が蘇った。「強く生きよ」と「優しく生きよ」と常に教えられたことが鮮明に思い出された。彼は自分を振り返った。強く生きてきた。しかし優しく…とまで考えた時、老人は切り出した。「お前に『強く生きよ』と教えた。しかしお前は強がって生きたに過ぎない。お前に『優しく生きよ』とも教えた。しかしお前は自分に優しく生きたに過ぎない」。さらに老人は「もとよりお前の性根は優しい。積み重ね来た行いにお前の善良な精神は耐えきれなくなったのだ。奥深く畳み込まれていたものが、心の襞(ひだ)を突き破って噴き出してきたのだ。鎧を下ろせ。自分らしく生きよ」。さらに朗々と「我を失うほど他に尽くせば、すなわち幸いなり」と言うや、刷毛で掃いたように消え去った。
どれだけの時間が経ったのか、気がつくと、彼はデスクに座っている。デスクの上にある名刺入れが彼の眼に入った、最初からあったかのように。電話機も書類ケースも元のままだった。名刺入れを手に取ると、そこには一枚の紙片が挟まれていた。紙片には「失我奉献 是則幸也」とだけある。自分の文字だ。その文字を見るなり祖父の言葉を思い出した。「我を失うほど他に尽くせば、すなわち幸いなり」他者に尽くすことが、自分を救うということか。彼は幾度となく反問した「俺は、それ程に傲慢だったか… 自分らしく…」。
窓に塗り込まれたような闇が溶け初めると急速に明るさを取り戻し、やがて山の端(やまのは)からまばゆい光が中天にむけて、矢のように放たれると、オフィスに光が満ちてきた。彼のおとがいにも柔らかい朝の光が届いた。その時、肩の力が解け、心の隅に何かが芽生えた。